ここまでAI、AIと再三再四その利便性をお伝えしてきたが、それと逆行するようなタイトルとなるのが今回の話題。「AIがあっても計算は必要?」という問いがその内容である。皆さんはどうお考えであろうか??
今回お伝えするのは『公益財団法人スプリックス教育財団』による基礎学力に対する意識の現状を把握することを目的に「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」の内容をまとめたもの。早速その内容を見てみよう。
調査結果のポイント
(1) 「AIがあっても計算力は必要」が多数派、ただし保護者と子どもに意識差
調査対象8カ国のうち7カ国で、「生成AIがあっても基本的な計算力は必要」との回答が70%以上でした。また、「計算力は必要」と答える割合は、7/8カ国で保護者のほうが子どもより高く、例えば日本ではその差が約10ポイントでした。(2) 計算に自信のない子どもほど、計算力は不要と考える傾向
計算力に自信がある子どもよりも、自信がない子どもの方が、「生成AIがあれば基本的な計算力は不要」と考える傾向がありました。自信のなさから、自ら計算しようとする意欲の低さにつながっている可能性が示唆されました。(3) 自信と計算力に一定の相関
「計算に自信がない」と回答した子どもは、計算テストの成績も低い傾向にあり、両者の間には一定の相関が見られました。これは、自信のなさが単なる主観的な思い込みではなく、実際の計算力の低さを反映している可能性を示しています。(4)日本では「保護者からの承認」が勉強意欲に強く結びつく
出典:AIがあっても計算は必要? ほとんどが必要と回答も、保護者と子どもの間に意識差ースプリックス教育財団 国際基礎学力調査より(公益財団法人スプリックス教育財団)
勉強意欲について調べたところ、日本の子どもは世界に比べて「テストで成績が上がる」「課題をやり遂げる」といった成果や達成感に加えて、保護者にほめられることが強い動機となっていることが分かりました。
以上、いかがであろうか。まぁ、子供としては苦手なモノを避けたい、というのはある程度仕方のないことかもしれないが。その隠れ蓑にAIを使う、というのはいかがなものか? というのが本当のところか。
何より便利さを感じるには、その前提となる知見が必要。それをベースに便利なものがなかった時と比較して、初めて「便利」と感じる訳なので。便利を知るには最低限の知識がいるんだよ、ということが分かるところまでは、しっかりと教育に機能してもらいたいところ、と言えよう。
出典:公益財団法人スプリックス教育財団 “AIがあっても計算は必要? ほとんどが必要と回答も、保護者と子どもの間に意識差ースプリックス教育財団 国際基礎学力調査より”

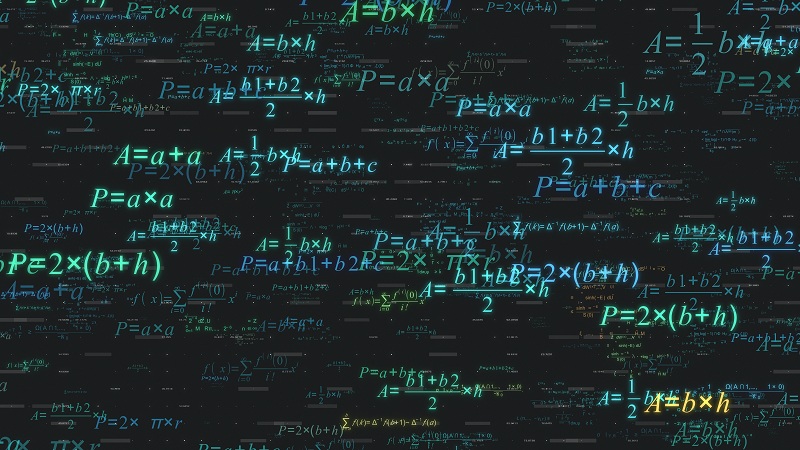
コメント